⑤熱量と比熱
📌 はじめに
物理分野で、ほぼ確実に出題される重要テーマが
「熱量・比熱・熱容量」です。
ポイントは、
- どれくらい温めたか(温度の変化)
- どれくらいの量があるか(質量)
- その物質が温まりやすいかどうか(比熱)
この3つを押さえるだけ。
この記事では、
「熱量って結局なに?」
「比熱と熱容量はどう違うの?」
といった疑問を、できるだけ専門用語を使わずに解説していきます。

🧠 1. 熱量って何?
**熱量(ねつりょう)**とは、物質に加えたり取り去ったりする 熱エネルギーの量 のことです。
単位は J(ジュール) や kJ(キロジュール) で表します。
1 kJ = 1000 J です。
🌡️ 2. セ氏温度と絶対温度(ケルビン)
熱の計算では、温度の単位として ケルビン(K) も使います。
これは 絶対温度 といって、温度が絶対に下がらない「ゼロ点」を基準にした温度です。
- ケルビンの値 = セ氏温度(℃)+ 273
- たとえば 0℃ は 273 K
- -273℃ は 0 K(絶対零度)です。
⚖️ 3. 比熱って何?
比熱(ひねつ) は物質ごとに決まっている値で、
➡ 物質 1 g の温度を 1℃(または 1 K)上げるのに必要な熱量 を表します。
単位は J/(g・℃) または J/(g・K) です。
具体的に言うと、
- 比熱が 大きい物質 → 温まり にくい、冷め にくい
- 比熱が 小さい物質 → 温まり やすい、冷め やすい
例:
水の比熱は 4.2 J/(g・℃)。
つまり、水 1 g の温度を 1℃ 上げるには 4.2 J の熱が必要です。
🧮 4. 熱容量って何?
熱容量(C) は、
➡ その物体全体を 1℃(または 1 K)上げるのに必要な熱量 のこと。
単位は J/℃ や J/K です。
熱容量は、質量が大きいほど大きくなります。
そして、
熱容量 C = 質量 m × 比熱 c
という関係があります。
🔢 5. 熱量の計算公式
熱量 Q(J)は次の公式で計算します:
Q = 比熱 c × 質量 m × 温度差 ΔT
- Q:熱量(J)
- c:比熱
- m:質量(g)
- ΔT:温度の変化(℃ または K)
つまり、
質量が大きいほど、比熱が大きいほど、温度を大きく変えるにはたくさんの熱が必要になります。
🔍 6. 例題(考え方が身につく)
水 100 g の温度を 10℃ 上げる場合:
- 比熱 c = 4.2 J/(g・℃) (水の場合)
- m = 100 g
- ΔT = 10℃
計算:
Q = 4.2 × 100 × 10 = 4200 J
つまり、この水を 10℃ 温めるには 4200 J の熱が必要 ということです。
📝 7. まとめ(試験対策)
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 熱量 | 熱のやり取りの量(J) |
| 比熱 | 1g を 1℃ 上げるのに必要な熱量(J/(g・℃)) |
| 熱容量 | 物体全体を 1℃ 上げるのに必要な熱量(J/℃) |
| 熱量公式 | Q = c × m × ΔT |
この分野は 公式を覚えて、計算の方向を理解してしまえば、得点につながりやすい分野 です。
練習問題をたくさん解いて、公式の使い方に慣れておきましょう。

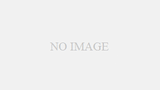
コメント