⑨イオン化傾向
化学的な腐食や金属の反応性を理解するうえで、「イオン化傾向」はとても重要です。
特に乙種4類では、金属がどれくらい電子を失いやすいか(=酸化しやすいか) をしっかり押さえておくことで、腐食のしくみや防食の考え方がすっと理解できるようになります。

🎯 1.イオン化傾向って何?
イオン化傾向とは、金属が水溶液中で
👉 陽イオン(Mn⁺)になろうとする(=電子を失う) しやすさ
のことです。
つまり、酸化されやすさの指標 と考えればOK。
- **イオン化傾向が大きい(強い)**金属 → 電子を失いやすい → すぐ陽イオンになる
- **イオン化傾向が小さい(弱い)**金属 → 電子を失にくい → 腐食しにくい
📊 2.イオン化傾向の順番(=イオン化列)
以下は、金属の陽イオン化しやすい順(=イオン化傾向が大きい順)です。
試験で出題されることもあるので、この順番は覚えておこう。文系でもOK!乙種4類合格への道
| Li | K | Ca | Na | Ma | Al | Zn | Fe | Ni | Sn | Pb | H | Cu | Hg | Ag | Pt | Au |
| リチウム | カリウム | カルシウム | ナトリウム | マグネシウム | アルミニウム | 亜鉛 | 鉄 | ニッケル | スズ | 鉛 | 水素 | 銅 | 水銀 | 銀 | 白金 | 金 |
語呂合わせにすると覚えやすいと思います。いろいろあるので調べてみると面白いです。
リカ(ちゃん)、カナ(ちゃん)まあ当てにすなひどすぎ借(白)金
| リ | カ | カ | ナ | ま | あ | 当 | て | に | す | な | ひ | ど | す | ぎ | 借 | 金 |
| Li | K | Ca | Na | Ma | Al | Zn | Fe | Ni | Sn | Pb | H | Cu | Hg | Ag | Pt | Au |
- 左ほど電子を失いやすく(酸化しやすく)、
- 右ほど失いにくい(酸化しにくい)。
例)
- Li(リチウム)はすぐ溶けて陽イオンになる → イオン化傾向大
- Au(金)はほとんど酸化されない → イオン化傾向小
🧪 3.イオン化傾向の意味(覚え方)
イオン化傾向の大小は、そのまま錆びやすさ・腐食しやすさにもつながります。
- イオン化傾向が大きい金属 → 水中で溶ける(腐食しやすい)
- イオン化傾向が小さい金属 → 簡単には溶けない(腐食しにくい)
📌 鉄のような金属は、イオン化傾向がそこそこ大きいので、錆びやすいと言えます。
反対に 金や白金 はイオン化傾向が小さいので、自然状態ではほとんど腐食しません。
🛡 4.腐食を防ぐには?
イオン化傾向を理解すると、腐食防止の方法も分かってきます。
✔ 腐食しやすい条件
- 水分・湿度がある
- 異なった金属が接触している
- 塩分や酸性条件がある場所
✔ 腐食防止の方法
- 防食材(塗装・樹脂など)で覆う
- イオン化傾向の大きい金属を保護材として使う
→ もっと酸化しやすい金属(例:亜鉛)を付けると、そちらが先に酸化(腐食)されて本体を守る仕組み(犠牲防食)。
🧠 5.受験者用まとめ
- イオン化傾向 = 金属が電子を失って陽イオンになる傾向
- イオン化傾向が大きいほど酸化しやすい(錆びやすい)
- 錆びを防ぐには、酸化しやすい金属を利用したり、腐食しにくい環境をつくることがポイント

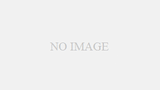
コメント