①燃焼
📌 はじめに
火災は、**「燃えるもの」「酸素」「火(熱)」**という条件がそろったときに発生します。
危険物取扱者乙種第4類で扱うガソリンや灯油などは、非常に燃えやすい性質を持っており、燃焼の仕組みを正しく理解していないと、思わぬ事故につながるおそれがあります。
乙4試験では、
- 燃焼が起こる条件
- なぜ消火できるのか
- 液体危険物がどのように燃えるのか
といった基本理論が頻出します。

🔥 1.燃焼とは何か?(試験で必ず出る基本)
燃焼 とは、
👉 可燃物(燃える物質)と酸素が結びつき、熱と光を伴って激しく酸化反応する現象 のことです。
- 燃焼が起こるには 3つの要素 がそろう必要があります👇
- 可燃物(燃える物質)
- 酸素(支燃物・酸素供給源)
- 点火源(熱源)(火・火花・静電気など)
この3つがそろってはじめて燃焼が起こります。逆に言えば、どれか一つを欠けさせれば燃焼は止められます。
🔥 2.燃焼が起こるための「3要素」
📌 燃焼の3要素
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 可燃物 | 木材・紙・ガソリンなど燃えやすい物質 |
| 酸素 | 空気中の酸素(約20%)、酸化剤など |
| 点火源 | 火・火花・静電気・衝撃熱など |
→ この3つが同時にあると燃焼が起こる。
→ どれか一つ欠けても燃焼は継続しない。
🔥 3.燃焼と消火(基本理論)
📌 消火の基本
消火とは燃焼を止めること
→ 燃焼の3要素(可燃物・酸素・点火源)のいずれかを断つことが消火の基本戦略です。
🔥 4.消火の方法(試験ポイント)
🔥 消火の基本3効果
| 消火方法 | どうやって消す? |
|---|---|
| 除去消火 | 可燃物(燃える物)を取り除く |
| 窒息消火 | 酸素の供給を遮断する |
| 冷却消火 | 熱を奪って火を消す |
※これらは「消火の三要素」とも呼ばれます。
🔥 5.燃焼のタイプ(物質ごとに燃え方が違う)
燃焼は物質の種類によって燃え方が異なります。これは乙4試験でもよく問われるポイントです。
🔹 ① 固体の燃焼
✔ 燃焼の仕組み
固体は、
👉 加熱されることで表面が分解・蒸発(熱分解)し、発生した可燃性ガスが燃える
という形で燃焼します。
※ 固体そのものが直接燃えているわけではありません。
✔ 特徴
- 燃焼は表面から徐々に進行
- 燃焼速度は比較的遅い
- 炭や木材のように**炎を出さずに燃える(無炎燃焼)**こともある
✔ 例
- 木材
- 紙
- 石炭
📝 試験ポイント
✔ 「固体は熱分解して生じた可燃性ガスが燃える」
🔹 ② 液体の燃焼【乙4最重要】
✔ 燃焼の仕組み
液体は、
👉 液体そのものは燃えず、表面から蒸発した可燃性蒸気が空気中で燃える
✔ 特徴
- 燃焼は液面付近で起こる
- 引火点以上でないと燃焼しない
- 蒸気が空気と混ざることで燃焼する
✔ 例(乙4危険物)
- ガソリン
- 灯油
- 軽油
- アルコール類
📝 試験ポイント(超重要)
✔ 「液体は蒸気が燃える」
✔ 「液体そのものは燃えない」
👉 ここは○×問題・選択問題で頻出です。
🔹 ③ 気体の燃焼
✔ 燃焼の仕組み
気体は、
👉 可燃性ガスが空気中の酸素と直接混合して燃える
✔ 特徴
- 燃焼は非常に速い
- 条件がそろうと爆発的燃焼を起こしやすい
- 炎が空間全体に広がることがある
✔ 例
- 水素
- メタン
- プロパン
📝 試験ポイント
✔ 「気体は空気と混合して燃焼する」
✔ 「燃焼速度が速い」
🧠 6. まとめ:試験で押さえるべきポイント
✔ 燃焼とは熱と光を伴う酸化反応
✔ 燃焼には可燃物・酸素・点火源の3要素が必要
✔ 消火は3要素のどれかを取り除くこと
✔ 液体の危険物は蒸発した蒸気が燃える仕組み

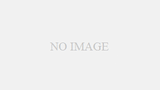
コメント