⑥溶液の溶解度・濃度 (学習時間目安15分)
溶液の濃度は、乙4試験や定期テストで必ず出る重要分野です。
しかし、
・溶質と溶媒の違いが分からない
・%濃度の計算でミスする
・モル濃度になると混乱する
という人も多いです。
この記事では、受験生向けに
「意味 → イメージ → 計算」
の順で、溶液の濃度をやさしく解説します。

1. 溶液・溶質・溶媒とは?
- 溶質:溶ける物質(例:食塩)
- 溶媒:溶かす物質(例:水)
- 溶液:溶質+溶媒
📌 試験ワンポイント
水溶液では「水=溶媒」と覚える!
2. 濃度とは何か?
濃度とは「溶液の中に、溶質がどれくらい入っているか」
を表したものです。
🍹 例:
- 薄いジュース → 濃度が低い
- 濃いジュース → 濃度が高い
👉 日常例を1つ入れるだけで理解度UP
3. 質量パーセント濃度【最重要】
✔ 定義
質量%濃度(%)=
溶質の質量 ÷ 溶液の質量 × 100
✔ 例題(必須)
例)食塩10gを水90gに溶かした。
質量%濃度は?
溶液の質量:10g+90g=100g
10 ÷ 100 × 100 = 10%
📌 試験ワンポイント
- 分母は「溶液」
- 水だけじゃない!
4. モル濃度【乙4頻出】
✔ 定義
モル濃度(mol/L)=
物質量(mol) ÷ 溶液の体積(L)
✔ 手順を分けて計算(超重要)
1️⃣ 溶質の質量 → モルに直す
2️⃣ mL → L に直す
3️⃣ 式に代入
5. よくあるミス(ここが差になる)
- ❌ 水の質量を分母にする
- ❌ mLのまま計算
- ❌ モル質量を間違える
6. まとめ【暗記用】
・溶質+溶媒=溶液
・%濃度は「質量」
・モル濃度は「molとL」
・単位を必ず確認!
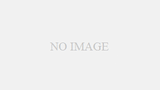
コメント