③自然発火・混合危険・爆発
📌 はじめに
燃焼の基本として「燃える条件」(可燃物・酸素・点火源)や「引火点・発火点・燃焼範囲」を押さえたら、次に理解したいのが、火災に発展する可能性を高める現象です。
この記事では、
✅ 外から火をつけなくても燃えることがある「自然発火」
✅ 物質同士の組み合わせで起こる危険「混合危険」
✅ 急激な燃焼で大きなエネルギーが放出される「爆発」
について勉強します。これらは、単なる燃焼の知識にとどまらず、安全管理・危険予測にも直結する重要ポイントです。

🔥 1. 自然発火
📌 自然発火とは?
自然発火とは、
👉 物質自身の内部で熱が生じ、加熱し続けられた結果、外から火をつけなくても発火・燃焼が始まる現象です。
外部の火・火花がなくても燃え始めるため、放置や密閉場所での発熱には注意が必要です。
✔ 原因となる熱の例
- 分解熱(化学分解による熱)
- 酸化熱(空気中で徐々に酸化されて発熱)
- 吸着熱(表面への吸着で発熱)
- 微生物活性による熱 など
✔ 日常例(覚え方)
- 石炭の山が熱を持つ
- 油脂やゴミの堆積が勝手に熱くなる
👉 これらは自然発火が起きている可能性があります。
🔥 2. 混合危険
📌 混合危険とは?
混合危険とは、
👉 二つ以上の物質が混ざることで、思わぬ発火・爆発の危険が生じる状態を指します。
単独では安全でも、組み合わせによって危険性が生じることがあるため、危険物取扱の現場では特に注意すべきポイントです。
✔ よくある危険な組み合わせ
- 酸化性物質 + 還元性物質
- 例:塩素酸カリウム(酸化性)+ 赤リン(還元性)
- 酸化性塩類 + 強酸
- 例:塩素酸カリウム+濃硫酸 → 不安定な遊離酸が生成
- 敏感な爆発性物質の生成
- 例:アンモニア+塩素 → 三塩化窒素(衝撃で爆発)
🔎 どちらも燃焼だけでなく爆発につながる可能性あり
🔥 3. 爆発
📌 爆発とは?
爆発とは、
👉 瞬時に大量のエネルギーが解放され、圧力と音を伴って急激に広がる現象です。
火災の一種に見えますが、燃焼よりはるかに急激で危険性が高い現象として区別されます。
🔥 4. 爆発の種類(乙4で押さえるポイント)
🔹 ① 粉じん爆発
- 微粒子の可燃物(粉じん)が空気中に浮遊
- 表面積が大きく、燃焼が一気に進む
👉 乾燥した環境ほど起きやすい
例:小麦粉、木材粉じん
🔹 ② 可燃性蒸気の爆発
- 液体の可燃性蒸気が“燃焼範囲”にある場合
- 密閉空間で火源が加わると、一気に燃焼・爆発する
🔹 ③ 気体の爆発
- 可燃性気体は燃焼速度が速く、爆発しやすい性質があります
例:水素、プロパンガス
📌 5. まとめ(試験で押さえるポイント)
| 現象 | 意味・特徴 |
|---|---|
| 自然発火 | 点火源なしで燃え始める |
| 混合危険 | 2物質以上の組合せで危険が生じる |
| 爆発 | 瞬時に大量のエネルギーと圧力が解放される |

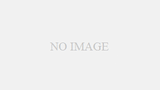
コメント