①危険物の分類
📌 はじめに
危険物乙種第4類の学習では、危険物そのものの性質をしっかり理解することが合格のカギです。
なぜなら、物質ごとの性質が分かれば、火災予防・消火方法・安全管理まで一連の流れで理解できるようになるからです。
まずは、危険物がどのようなグループ(類)に分けられているのかを押さえましょう。これは試験でも基礎となる重要分野です。

🔥 1. 危険物とは?
消防法における「危険物」とは、
👉 火災が発生しやすく、消火が困難な性質を持つ物質の総称です。
危険物は化学的性質や火災に関連する性状によって、第1類〜第6類までの6グループに分けられています。
(※危険物は個体・液体のみで、気体は含まれません)
🔹 2. 危険物の類別一覧(6類)
🧪 第1類:酸化性個体
- 性質:自身は燃えないが、他の物質を強く酸化させる
- 火災リスク:可燃物と混ざると熱・衝撃・摩擦で激しく燃焼や爆発を起こす
- 例:塩素酸塩類・過マンガン酸塩類など
🔥 第2類:可燃性個体
- 性質:火炎で着火しやすく、比較的低温で燃焼
- 火災リスク:燃焼しやすく、消火が困難
- 例:硫黄・赤リン・マグネシウムなど
🔥 第3類:自然発火性物質・禁水性物質
- 性質①:空気中で自然に発火
- 性質②:水と反応して発火または可燃性ガスを発生
- 例:黄リン・アルカリ金属・アルキルアルミニウムなど
🔥 第4類:引火性液体(※乙4 試験の対象)
- 性質:液体だが蒸気が引火性を持つ
- 例:ガソリン・灯油・軽油・アルコール類など
👉 ここが 乙種第4類試験の本丸。「引火性液体」の性質と扱い方を深く学習します。
🧨 第5類:自己反応性物質
- 性質:分解や加熱で大量の熱を発生、場合によっては爆発的に反応進行
- 例:有機過酸化物・アゾ化合物など
🧪 第6類:酸化性液体
- 性質:自身は燃えないが、他の物質(可燃物)の燃焼を促進
- 例:過酸化水素・硝酸など
📊 3. 性質と危険性のポイント
| 類別 | どんな性質? | 火災との関係 |
|---|---|---|
| 1類 | 酸化作用あり | 可燃物との反応で激しく燃える |
| 2類 | 燃えやすい固体 | 火源で一気に燃焼 |
| 3類 | 自然発火・禁水性 | 空気や水と反応して発火 |
| 4類 | 引火性液体 | 蒸気が引火して火災 |
| 5類 | 自ら熱発生 | 熱で分解・爆発 |
| 6類 | 酸化促進する液体 | 火災を助長する |
※危険物は 固体と液体のみ(気体は分類に含まれません)
🧠 4. 受験者向け暗記ワード
- 第1類:酸化性個体(酸素を供給して燃えやすくする)
- 第2類:可燃性固体(着火しやすい)
- 第3類:自然発火性/禁水性(空気・水で危険)
- 第4類:引火性液体(蒸気が主役)
- 第5類:自己反応性(熱・爆発)
- 第6類:酸化性液体(燃焼を助ける)
👉 特に第4類は 火災の中心テーマ です!
📌 5. まとめ(試験での出題イメージ)
- 危険物は 性質で分類される
- 第4類(引火性液体) は乙4試験の中心
- それぞれの類で 何が危険か を理解することが合格につながる

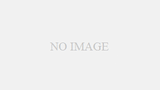
コメント