②第4類危険物
📌 はじめに
引火性液体の性質と基礎ポイント
危険物取扱者乙種第4類の学習でまず押さえたいのが、「第4類危険物」の性質です。
この分類は 身近な液体(ガソリン・灯油・アルコールなど)がなぜ危険なのか を理解する入り口になり、試験でも非常によく出題されます。
実は「液体」そのものが危険なのではなく、その液体から出る“蒸気”が引火しやすいこと が火災リスクの大部分を占めています。
これをしっかり押さえると、単なる丸暗記ではなく「理屈で覚える勉強」ができるようになります。

📌 1. 第4類危険物って何?
第4類危険物=すべて「引火性液体」
という理解でOKです。
引火性液体とは、常温でも蒸気が発生し、火気(火や静電気など)に触れると すぐに引火したり爆発したりする可能性がある液体 を指します。
つまり、第4類は
👉 液体=目で見える状態だけ危険なのではなく
👉 そこから発生する蒸気が一番のリスク
と思っておくと学習がしやすくなります。
🧪 2. 第4類危険物の「分類」
第4類危険物は、引火点の違いによって次のように細かく分けられています:
| 分類 | 引火点の目安 | 具体的な物質 |
|---|---|---|
| 特殊引火物 | -20℃以下 | ジエチルエーテル、二硫化炭素 |
| 第1石油類 | 21℃未満 | ガソリン |
| アルコール類 | 約11〜23℃ | エタノール |
| 第2石油類 | 21〜70℃未満 | 灯油、軽油 |
| 第3石油類 | 70〜200℃未満 | 重油 |
| 第4石油類 | 200〜250℃未満 | ギヤー油、シリンダー油 |
| 動植物油類 | 250℃未満 | アマニ油 |
| 👉 ※ 引火点が低いほど “引火しやすい危険物” です。 |
⚠️ 3. なぜ第4類は危険なの?
第4類危険物の特徴は次のような点です:
🔥 引火しやすい
液体が蒸発して 可燃性の蒸気を出しやすく、火気・静電気・摩擦などで簡単に火がつく。
💧 多くは水に浮く
水より軽い液体が多く、こぼれると 水面に広がって燃えやすい面が大きくなる危険もあります。
🌫 蒸気は空気より重い
発生した蒸気は空気より重く 低い場所に溜まりやすいため、気付かないうちに引火源に近づくことがある。
⚡ 静電気にも注意
多くの引火性液体は 静電気を発生しやすく、ほんの小さな放電でも引火するリスクがある と覚えておきましょう。
🛟 4. 取扱い上の注意(基本)
第4類危険物を扱うときは以下が大前提です:
✔ 火気厳禁
✔ 換気を十分に行う
✔ 漏れた液体・蒸気を迅速に除去・換気
特に 火気(タバコ・火花・静電気など)が最大の敵 です。
安全対策の基本は “引火しやすい蒸気を発生させない・溜めない” ことです。
🧯 5. 消火の基本
水はNG!
引火性液体火災の消火は次が基本になります:
- 泡消火剤
- 二酸化炭素
- 粉末消火器
- ハロゲン化物消火剤
これらは 酸素遮断や燃焼反応抑制 を狙った消火方法で、水だと逆に火勢を広げてしまうことがあるためです。
📝 6. まとめ
💡 第4類危険物=引火性液体のこと。
液体そのものより、蒸気が引火する性質を理解する のが合格のポイントです。
✔ 引火点が低いほど危険
✔ 蒸気は空気より重い
✔ 火気と静電気に最大注意
✔ 消火は水以外の方法

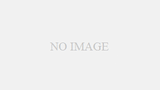
コメント