⑧屋外貯蔵所の基準
📌はじめに
「屋外貯蔵所」 は、建物の外で危険物を貯蔵する場所として、火災や漏洩による事故を防ぐために 構造・貯蔵方法・対象となる危険物の種類 について明確な基準が設けられています。以下では、屋外貯蔵所の基準を主要ポイントごとに整理します。

🔎 1. 屋外貯蔵所とは?
屋外貯蔵所とは、屋根や天井のない屋外で危険物を貯蔵する場所を指し、建築物内部とは異なる独自の基準が適用されます。
危険物の性質や数量に応じて、空地や囲い、積み重ね高さなども規定されています。

🧱 ① 貯蔵場所の構造基準
屋外貯蔵所は安全性を確保するために、次のような 構造上の条件 が定められています:
- 保安距離と保有空地 が必要で、危険物の周囲には柵などで区画する。
- 保有空地の幅は危険物の数量によって異なる(例:指定数量×500倍以下であれば空地3 m以上、500倍超1,000倍以下は5 m以上)。
- 屋外貯蔵所には 屋根や天井がない(=屋外であることが前提)。
これらは、万一災害が発生した際に熱やガスがこもらないようにし、周囲への被害を最小化するための基準です。
📦 ② 容器の貯蔵方法
危険物を貯蔵する際の 容器の扱い方法 に関しては以下のような基準があります:
- 危険物は 基準に適合した容器に収納して貯蔵 する必要がある。
- 容器の積み重ね高さは基本 3 m以下。
- 架台を使用する場合でも高さは 6 mを超えない。
このような制限は、倒壊や破損による漏洩リスクを抑えるために定められています。
🧪 ③ 貯蔵できる危険物の種類
屋外貯蔵所で 貯蔵できる危険物の種類 は制限されており、代表的な例は以下の通りです:
- 主に 第2類危険物(硫黄など) や、 第4類危険物のうち引火点が40 ℃以上のもの が対象。
- 引火点が低いもの(ガソリンやベンゼン、特殊引火物など) は屋外貯蔵所では 貯蔵できない。
- 水と反応して危険なものや自然発火性のある物質も同様に対象外。
これらの区分は、火災や爆発の危険性が高い物質の安全確保のために設けられています。
📌 2. まとめ(重要ポイント)
✔ 構造:保安距離・保有空地の確保、屋根や天井なしで屋外であること。
✔ 貯蔵方法:基準容器、積み重ね高さ制限(3 m/6 m)。
✔ 対象危険物:第2類や引火点が高い第4類中心、低引火点物質はNG。

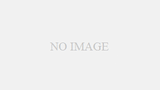
コメント