②沸騰と沸点
📌 はじめに
「沸騰」や「沸点」は、乙種危険物取扱者試験でもよく問われる基本用語です。
どんな条件で液体が気体になるのか、沸点がどう決まるのかを正しく理解しておくことが大切です。

🔹 1.沸騰とは?
✔ 沸騰 とは、液体全体から 気体が急に大量に発生する状態変化 です。
- 液体を加熱すると、液面だけでなく内部からも気泡が出ます。
- これが沸騰です。
【ポイント】沸騰は「液体内部から気体が発生する」状態変化です。
🔹2. 沸点とは?
✔ 沸点 は、液体が沸騰を始める 温度のこと です。
- 沸点の温度では、液体の 飽和蒸気圧と外側の圧力が等しくなる 状態になります。
- この条件を満たすと、液体表面だけでなく内部でも気体が発生して沸騰が起こります。
🔹 3.飽和蒸気圧と沸点の関係
一定の温度において蒸気が示す最大圧力のことを『飽和蒸気圧』という。
- 飽和蒸気圧の値は液体の種類や温度によって変わる。
- 温度が上がれば飽和蒸気圧も上がる。
- 「飽和」とは最大まで満たされた状態のこと。
液体が加熱されると、液体表面に逃げようとする蒸気の圧力(飽和蒸気圧)が上昇します。
沸騰が起こるのは、この蒸気圧が外側(大気圧)と等しくなった時 です。
- 飽和蒸気圧 = 外圧(例:1気圧) ➝ ここで沸騰が始まる
- 外圧が変わると沸点も変わります。
- 大気圧が 高い → 沸点は 高い
- 大気圧が 低い(高地など) → 沸点は 低い
※これは圧力鍋でも同じ原理です(蓋で密閉して圧力を上げると沸点が上がる)。
🔹 4.身近な例でイメージ
- 標準大気圧(1気圧)では、水の沸点は 100℃
→ 100℃以上にしても温度が上がらず、沸騰が継続します。 - 高地(気圧が低い場所)では水は 100℃より低い温度で沸騰する
→ 同じ熱でも沸騰によって温度が上がりにくいため、調理に時間がかかります。
🔹 5.融点と凝固点との違い
状態変化を理解するうえで、沸点と似ている用語があります:
✔ 融点
- 固体 → 液体になる温度
- 例:氷が水になる温度(0℃ ※同じ圧力では凝固点と一致)
✔ 凝固点
- 液体 → 固体になる温度
- 同じ圧力条件下では 融点と同じ温度になります
→ どちらも、温度が変わらず熱エネルギーが 状態変化のためだけに使われる ためです。
🧠 6.受験者向けポイント整理
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 沸騰 | 液体内部からも気泡が出る大規模な蒸発 |
| 沸点 | 飽和蒸気圧 = 外圧になり沸騰が起こる温度 |
| 飽和蒸気圧 | 一定温度で気体が液面に及ぼす最大の蒸気圧 |
| 融点・凝固点 | 固体 ⇄ 液体 の変化温度(同じ圧力下で一致) |
✏️ 7.受験者用まとめ
✔ 沸騰は液面だけでなく 内部でも気体が発生する状態変化
✔ 沸点は 外圧と蒸気圧が釣り合う温度
✔ 沸点は 圧力によって変わる
✔ 融点と凝固点は 同じ圧力なら同じ温度

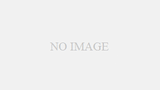
コメント