⑥熱の移動と熱膨張
📌 はじめに
この単元は日常生活のイメージがしやすく、実はかなり理解しやすい分野です。
たとえば、
- 金属のスプーンがだんだん熱くなる
- お風呂のお湯が自然に温まる
- 太陽の熱を遠くから感じる
これ、実はすべて「熱の移動」の話なんです。
この記事では、
- 熱はどんなルールで動くのか
- 熱伝導・対流・放射の違い
- 試験ではどこを押さえればいいのか
を、できるだけ難しい言葉を使わずに解説していきます

🔥 1. 熱の移動とは?
熱(熱エネルギー)は、温度が高い方から低い方へ必ず移動します。
この “熱が動くしくみ” を知っていると、危険物の物理問題でも点が取りやすくなります。
🌀 2. 熱が移動する3つの方法
熱の移動には、大きく分けて 3つの基本パターン があります。
どれも「高い温度 → 低い温度へ動く」という共通点があります。
① 熱伝導(ねつでんどう)
物質の内部や物体どうしが直接くっついている時に起こる熱の移動です。
熱は高い所から低い所へ “伝わっていきます”。
- 例: 熱い金属の一端を持つと、もう片方も熱くなる。
- 金属は熱を伝えやすい(熱伝導率が大きい)ですが、空気などは熱を伝えにくいです。
② 対流(たいりゅう)
液体や気体が実際に“流れる”ことで熱が運ばれる移動です。
- 例: お風呂の湯が上の方があたたかく、下が冷たいのも湯の動きによるもの。
- 空気や水などの流れ(熱い部分が上昇し、冷たい部分が下降する)によって熱が移動します
③ 放射(ほうしゃ)
物質がなくても熱が移動する方法です。
熱は電磁波(光に近い波)として直接伝わります。
- 例: 太陽の熱が宇宙を通って地球に届くのはこの現象。
- 物体同士が接していなくても熱が届くのが特徴です。
🌡️ 3. 熱膨張とは?
**熱膨張(ねつぼうちょう)**とは、
👉 物質が温められると体積が大きくなり、冷やされると小さくなる現象 のことです。
身近な例では、
- 夏に電線がたるむ
- 温度計の液体が上に伸びる
- ガラス瓶のフタが固いとき、お湯をかけると開きやすくなる
これらはすべて 熱膨張 が原因です。
🔥 なぜ熱膨張が起こるの?
物質は、目に見えなくても 原子や分子が集まってできています。
温められると、
- 原子や分子が激しく動く
- その結果、間隔が広がる
- 全体として体積が大きくなる
これが熱膨張の正体です。
逆に冷やすと、動きが小さくなり、体積は縮みます。
📦 熱膨張の3つの種類(試験頻出)
熱膨張には、次の 3つの種類 があります。
乙4試験では、この分類がよく問われます。
① 線膨張(せんぼうちょう)
棒や線のような形の物体が、長さ方向に伸びる膨張です。
- 主に 固体(金属など) で考える
- 温度が上がる → 長くなる
例:
- 鉄のレールが夏に伸びる
- 金属棒が加熱で長くなる
👉 「長さ」が変わる → 線膨張
② 面膨張(めんぼうちょう)
板状の物体が、面積として広がる膨張です。
- 実際は線膨張が2方向に起こったもの
- 試験では補足的な扱いが多い
👉 「面積」が変わる → 面膨張
③ 体膨張(たいぼうちょう)
物体全体の体積が大きくなる膨張です。
- 液体や気体で特に重要
- 固体でも体積は増える
例:
- 温度計のアルコールや水銀
- 温められた空気が膨らむ
👉 「体積」が変わる → 体膨張
🌡️ 4. 液体と気体の熱膨張
🔹 液体の熱膨張
液体は温められると 体積が増えます。
この性質を利用しているのが 液体温度計 です。
⚠ 注意点
容器(ガラス)も一緒に膨張するため、
見かけの膨張 と 真の膨張 という考え方があります。
(※乙4では深追い不要。用語を知っていればOK)
🔹 気体の熱膨張(重要)
気体は 特に膨張しやすい のが特徴です。
- 温度が上がる → 体積が増える
- 温度が下がる → 体積が減る
そのため、気体の計算では
👉 絶対温度(K:ケルビン) を使います。
📐 5. 熱膨張と温度の関係(気体)
気体では、
体積は絶対温度に比例する
という重要な性質があります。
つまり、
- 温度(K)が2倍 → 体積も約2倍
- 温度が下がる → 体積も小さくなる
この考え方は、
ボイル・シャルルの法則 につながる基礎です。
💡 受験で押さえるポイント
- 熱は 高温 → 低温へ移動する。これが基本です。
- 熱の移動の種類(伝導・対流・放射)は、試験でも 頻出テーマ です。
- 日常の例を浮かべながら覚えると、理解が早くなります!
📝 試験対策まとめ
熱の移動の基本は、
➡ 温度が高い方から低い方へ必ず移る
ということです。
その移り方は主に次の3つ:
| 方法 | 移動の仕方 | 例 |
|---|---|---|
| 熱伝導 | 物体の内部や接触で熱が直接伝わる | 熱い金属の先が暖かくなる |
| 対流 | 流体(空気・水など)が動くことで熱が運ばれる | お風呂の湯が対流で温まる |
| 放射 | 物質なしでも電磁波で熱が届く | 太陽の熱が地球に届く |
✅ 熱膨張とは
→ 温めると膨らみ、冷やすと縮む現象
✅ 熱膨張の種類
- 線膨張:長さ
- 面膨張:面積
- 体膨張:体積(液体・気体で重要)
✅ 気体は特に膨張しやすい
→ 計算では 絶対温度(K) を使う

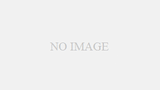
コメント