⑦静電気
📌 はじめに
静電気は「電気が 止まったまま たまる現象」です。
引火性の危険物を扱う現場では、静電気の放電(火花)が点火源 になることもあるため、仕組みを理解しておくことがとても大切です。特に非導体の液体や器具は電荷が逃げにくく、静電気がたまりやすいです。
特に、危険物乙4で扱う液体(ガソリン・灯油など)は電気を通しにくい(絶縁体)ため、静電気がたまりやすく、正しい理解が重要です。

🔹 1. 静電気とは?
✔ 静電気 とは、物体の表面に 電気(電荷)がたまった状態 のことです。
- 電気が流れているわけではなく とどまっている ので「静」電気と呼ばれます。
電気は、原子の周りにある 電子(マイナス) と 原子核の陽子(プラス) で構成されます。通常はプラスとマイナスが同じで中性ですが、摩擦などで 電子が移動するとバランスがくずれ、静電気が発生します。
🔄 どんなときに静電気が発生する?
静電気は主に次のようなときにたまります👇
✅ 摩擦で発生
- 異なる物質同士がこすれると 電子が移動し電荷がたまる
例:カーペットを歩く → 体に電気がたまる(静電気)
🔹 3. 電気がたまる物質の性質
物質は電気を通しやすいかどうかで2タイプに分かれます:
| 種類 | 電気の流れ | 静電気がたまりやすい? |
|---|---|---|
| 導体 | 電気が流れやすい(例:金属) | たまりにくい |
| 絶縁体 | 電気が流れにくい(例:プラスチック・油類) | たまりやすい |
※ 危険物乙4で扱う多くの液体は 絶縁体に近い性質 を持つため、静電気がたまりやすい状況が生まれます。
⚡ 4. 静電気が起こす現象
静電気がたまると、次のような現象が起こります:
🔹 引きつけ・反発
電気を帯びた物体同士は
- 同じ電気(++/--) → 反発
- 違う電気(+-) → 引きつけ
という力が働きます。
例:風船をこすって髪に近づけると髪が風船に引き寄せられることがあります。
🔥 5. 静電気放電(火花)の危険性
静電気がたまっていたものが、金属などの 電気を通すものに触れた瞬間、
👉 たまっていた電気が一気に流れ(放電)火花が出ることがあります。
これを 静電気放電 といいます。
- 小さな火花でも、可燃性蒸気や粉じんがある現場では 点火源になる危険性 があります。
📌 6. 静電気がたまりやすい条件(対策につながる)
静電気がたまりやすいのは次のような状況です:
☑ 摩擦や撹拌中
配管・ホース・ポンプで液体を移動させる際に摩擦が起こると静電気が発生します。
☑ 乾燥している空気
湿度が低いと電気が逃げにくく、静電気がたまりやすくなります。
☑ 絶縁体(非導体)
電気が逃げにくい物質は静電気がたまりやすいです。
☑ 摩擦以外にも帯電する状況まとめ。
- 接触帯電・・・2つの物質を接触させ、離すときに帯電する
- 流動帯電・・・液体が管内を流れるときに帯電する
- 沈降帯電・・・流体中を他の液体または個体が沈降するときに帯電する
- 破砕帯電・・・個体を砕くときに静電気が発生する
- 噴出帯電・・・液体が高速で噴き出すときに帯電する
- 誘導帯電・・・帯電した物体の近くの物体も、影響を受け帯電する
✏️ 7. 受験ポイント
- 「静電気がなぜたまるのか」「導体と絶縁体の違い」
→ この理解が実務的な安全対策(アースや加湿、流速を遅くするなど)につながるポイントです。
🧠 8. 受験者向けまとめ(暗記用)
- 静電気 = 電気がとどまってたまった状態(流れていない電気)。
- 電子の移動によって物体が +(正)/-(負) に帯電する。
- 導体 は電気が逃げやすい、絶縁体 はたまりやすい。
- 放電(火花)は 静電気が一気に移動する現象。
- 危険物の取り扱いでは 火花が点火源になりうる ので要注意。

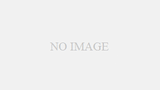
コメント